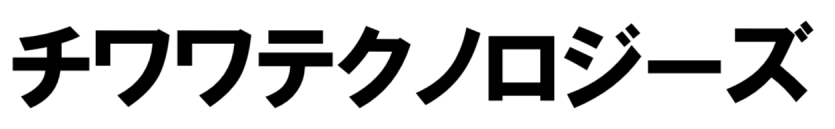まるで人間のように「時間を使って考える」新しいAI──CTMとは?
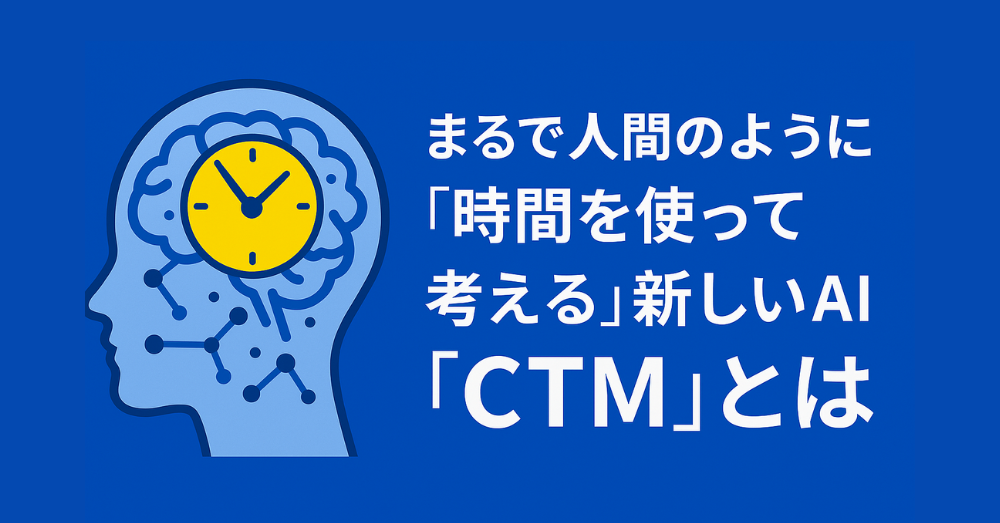
AI技術の進化は目覚ましく日々新しいニュースが飛び込んできます。2025年5月12日に日本発のAI企業「Sakana AI」から未来のAIに一歩近づくかもしれない革新的な技術が発表されました。その名もCTM(Continuous Thought Machine)。このCTMは、これまでのAIとは異なるアプローチで“考える”ことができる、新しいタイプのAIとして注目されています。
本記事ではこのCTMがどんな技術なのかを分かりやすく解説します。
CTMって、どんなAIなの?
私たちが普段接しているAI、たとえば画像認識や翻訳などのAIは非常に高性能ですが、どちらかというと「一瞬の判断」や「パターン認識」をおこなうAIです。それに対してCTMは人間が考えるときのプロセスにヒントを得て開発されました。私たちが難しい問題に直面するとき、情報を集めたり順番に整理したり時間をかけて考えたりしますよね? CTMはその「時間を使って段階的に思考する」という性質をAIの中に取り入れた点が特徴です。
CTMが使う「時間」の仕組みとは?
生物の脳の神経細胞(ニューロン)の働きでは、「どのくらい強く反応するか」だけでなく「いつ反応するか」や「ほかの細胞とどれだけ同期しているか」が非常に重要です。CTMは、このニューロンのタイミングや同期性に着目し、それをAIモデルの中核的な仕組みとして取り入れています。
たとえるなら、従来のAIが「はい、これを見て即判断!」という短距離ランナー型だとすれば、CTMは「まずここを見て、次はここ……」と時間をかけてじっくり考える長距離ランナー型のAIと言えるでしょう。
従来のAIとの違いは?
CTMの特長を、従来のAIとの違いを交えて見てみましょう。
1. 時間情報の活用
従来のAIは、主に「どれだけ強く反応したか(重み)」に注目していましたが、CTMは「いつ反応するか」や「他との同期」といった時間的要素を重視します。これにより、AI内部でより多様で柔軟な活動パターンが生まれます。
2. 段階的な思考プロセス
CTMは、問題を解くときに複数のステップを踏んで進みます。画像認識のタスクでも、一瞬で判断するのではなく、さまざまな部分に順を追って注意を向けながら考えるのです。
3. 問題に応じた柔軟性
CTMは、問題の難易度に応じて思考時間を調整できます。簡単な問題はすばやく、難しい問題はじっくりと対応するといった、思考の時間を“変化させられる”柔軟さがあると考えられています。
4. 思考の見える化
CTMは時間を使って思考するため、「どこに注目して、どう考えたか」が追跡可能です。これによりAIの判断過程が理解しやすくなり、ブラックボックス問題の解消にもつながります。
ユーザーにとって何が嬉しいの?
特に注目すべきは、「思考の見える化」です。AIがどうやってその答えを出したのかを時間経過とともに可視化できるため、結果の正当性を検証しやすくなります。これにより、AIの判断に対する信頼性や透明性が高まることが期待されています。
CTMの課題
CTMはまだ研究初期段階にあり、今後の課題として
- 現在主流のAIモデルと、様々なタスクで本格的に性能比較を進めること
- より幅広いタスクでの有効性を検証すること
などが挙げられています。
CTMに期待されること
CTMのような「時間」や「思考」を重視する新しいAIモデルからは、様々な可能性が期待されます。
1.AIの性能と効率の向上
生物の脳の仕組みを取り入れることで、今よりもさらに高性能かつ省エネなAIが実現するかもしれません。
2.脳科学への貢献
CTMの研究を通じて、人間の認知や思考における時間の役割について、神経科学的な理解が深まる可能性もあります。
3.より人間らしい、信頼できるAIの実現
段階的に思考し、そのプロセスが見えるAIは、より私たちの感覚に近い、理解しやすく信頼できるAIにつながる可能性があります。
まとめ:CTMはAIの未来に向けた重要な一歩
CTMは、従来のAIとは異なるアプローチで「時間」と「思考」を活用する、非常に興味深い新しいAIモデルです。まだ研究は始まったばかりですが、生物の脳からヒントを得たこの仕組みが、将来、「より高性能」で「より効率的」で私たち人間にとって「より分かりやすく、信頼できるAI」の実現につながる可能性を秘めています。
これからのCTMの進化が、AIの未来をどう切り拓いていくのか。ぜひ注目していきましょう。
気になる方はSakana AIの公式サイトもチェックしてみてください!
Sakana AIブログ:「時間を使って考える」AIの新パラダイム、Continuous Thought Machine(CTM)を提案