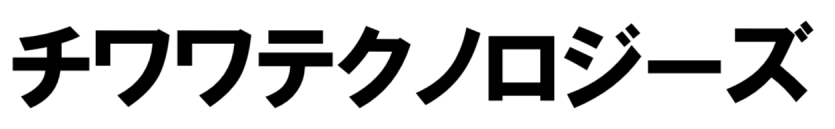生成AIの導入はなぜ進まない?中小企業の現状と今後の展望
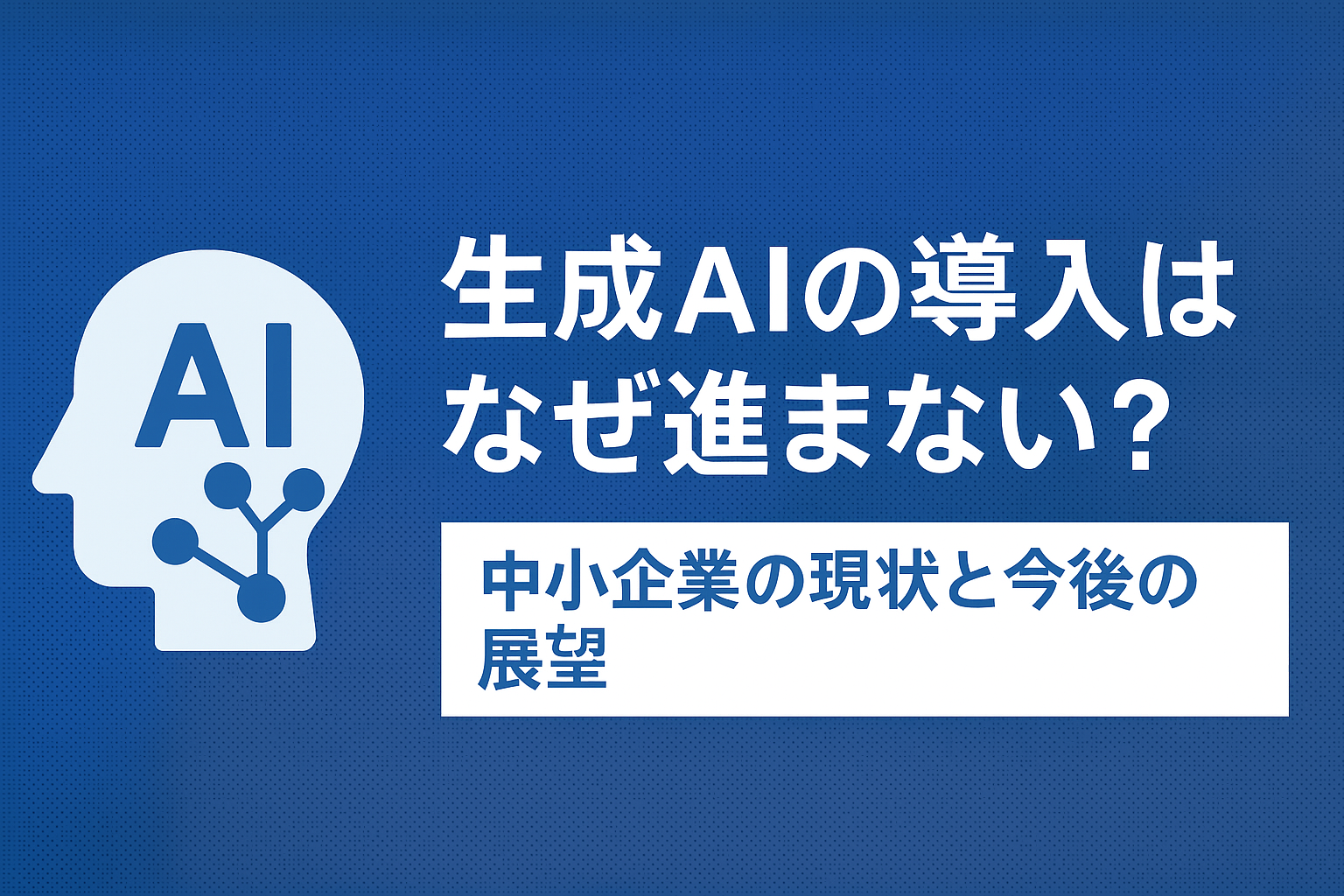
2025年5月12日にデル・テクノロジーズから「中小企業のPC・IT動向調査2025冬」が発表されました。調査結果では国内の中小企業における生成AIの導入状況と課題が詳細に分析されています。この記事では調査結果を分かりやすく要約してご紹介します。
生成AI導入率は15%、だが4割が効果を感じていない
調査によれば生成AIを既に業務に導入している企業は全体の15%にとどまります。さらに、そのうちの約4割が導入効果を感じていないと回答しています。一方、導入に前向きな企業は3割以上存在しており、多くの経営者が生成AIに可能性を感じていることは明らかです。導入が進んでいる業種には、情報・通信、不動産、教育、金融などがあり、いずれもデジタル活用に前向きな傾向が見られます。
成果が出ない理由とは?
導入が進まない、または成果が出ない理由として多く挙げられたのが、「活用するためのノウハウがない」「活用方法がない」という課題です。「何に使えばよいのか」「どう使えば効果が出るのか」という判断ができない状態で、導入に踏み切れない企業が多く見受けられます。 さらに、生成AIを使いこなす人材の不足、導入効果の不明瞭さ、セキュリティや法的リスクへの懸念も企業の足を止める要因となっています。
実際の利用状況から見えること
「まだ導入していないが使ったことがある」という企業も含めると、約半数の企業が何らかの生成AIを利用した経験があることが分かりました。最も利用されているのはChatGPT(無償版)で、次いでMicrosoft Copilot、Google Geminiと続きます。多くの企業が複数のサービスを併用しており、自社の業務に最適な生成AIを模索している段階にあることがうかがえます。
活用の中心は定型業務、創造的な業務にも期待が高まる
生成AIの活用業務として最も多く挙げられたのは、定型業務の効率化です。たとえば、メール返信、議事録作成、文書作成といった、日常的に発生するルーチン作業への活用が進んでいます。 さらに、人材不足に対応するために、属人化している業務の一般化や非定型業務の仕組み化にも活用が期待されています。特に製造業では、アイデア出しや新製品の企画など創造的な業務への活用に高い関心が寄せられており、生成AIのポテンシャルが新たな価値創出にまで及んでいることが見えてきました。
普及に必要なのは「使いやすさ」と「安心感」
生成AIの本格普及に向けて、企業が求めているのは以下の3点です。
- ノウハウや活用事例の提供
- 費用対効果の「見える化」
- 操作の簡易性とサポート体制
また、セキュリティや著作権リスクへの対応も重要です。多くの経営者が、安心して使えるAI環境の整備を前提として、導入の是非を判断しています。
生成AIを「試す」から「使いこなす」へ
今回の調査から明らかになったのは、「興味はあるが使いこなせていない」という現場の実態です。しかし、既に生成AIを活用して業務効率化や創造的な変革に取り組んでいる企業も現れており、ここに大きな競争力の差が生まれようとしています。
今後の展望として経営者に求められるのは、「どの業務で、何のために生成AIを使うか」を明確にすることです。そして、小さな業務から段階的に試し、成功体験を積み重ねることが重要です。
生成AIはもはや大企業だけの道具ではありません。人手不足やコスト上昇に悩む中小企業こそ、目的を持って導入すれば大きな武器になります。2025年は中小企業にとっての生成AIが「選択肢」から「戦略」に変わる時期です。まずは自社に合った一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。